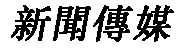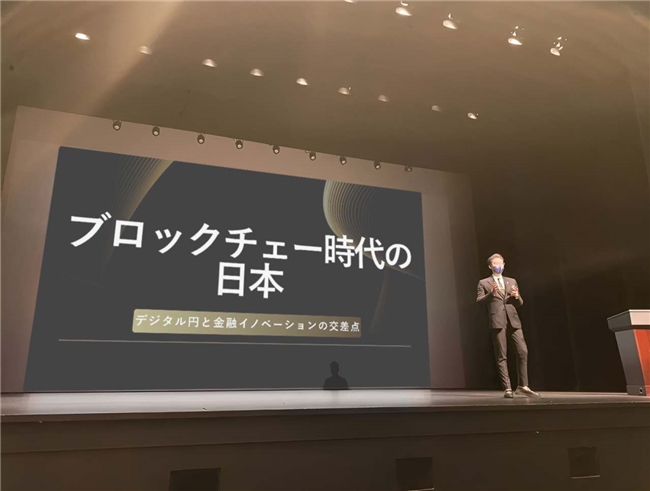
— 「安定性で稼ぐ」時代へ、見崎佑貴氏(CFA・FRM)が語る日本型ステーブルコイン戦略 —
【東京 2025年11月】日本銀行(BOJ)が進めるデジタル円の実証実験と並行し、民間主導による円建てステーブルコイン市場が急速に拡大している。改正資金決済法の施行により、銀行や信託会社、登録資金移動業者が発行主体となる体制が整い、2025年には市場規模が1兆5,000億円規模に達するとの見方も出ている。この新市場で注目されているのが、「安定性そのものが収益を生む」という日本独自のモデルだ。
国際的な金融資格CFAおよびFRMを保有する見崎佑貴氏は、東京・丸の内で開催された講演で次のように語った。「ステーブルコインは“リスクを取らずに利回りを生み出す”という点で、金融イノベーションの最前線にある。従来の仮想通貨が価格変動を基盤に収益を得ていたのに対し、日本のステーブルコインは信頼と金利差を基盤に収益を形成している。」
日本のステーブルコイン構造:制度がもたらす「収益の秩序化」
2023年に施行された改正資金決済法により、円建てステーブルコインの発行主体は銀行、信託会社、登録資金移動業者に限定された。これにより、発行資金は預金や信託財産として分別管理され、預金保険制度の対象となる安全設計が実現している。見崎氏はこれを「信用創造に依存しない利回りを許容する制度的デザイン」と位置付ける。
銀行が発行主体となる場合、預け入れ資金は国債やコマーシャルペーパーなどの短期安全資産に運用される。この運用利差(年0.5〜1.5%程度)が、ステーブルコイン事業者にとって主要な収益源となる。「国債金利が上昇する局面では、発行残高そのものが収益エンジンとなる」と同氏は指摘する。

市場拡大と利回りモデル
三菱UFJ信託銀行が開発する「Progmat Coin」や、みずほ・三井住友両グループによる共同構想が実証段階に入っている。これらは「規制の枠組みに基づく利差モデル」として位置付けられ、金融機関や企業間決済、証券型トークン(ST)との連携が進んでいる。
・発行側の収益:預託資金の運用利差や発行手数料
・利用者の利点:即時決済、コスト削減、海外送金の効率化
・投資家の利益:安全資産としての金利収益や流動性提供による手数料収入
見崎氏は「日本のステーブルコインは、規制を敵視せずに共存し、制度・信頼・収益を両立させている点で世界的にも稀有な存在だ」と語る。
社会的価値創造と「善の循環」
見崎氏は、ステーブルコインをはじめとする新たな金融インフラが、経済効率の追求にとどまらず、社会的価値を再分配する仕組みとしても機能し得ると指摘する。
「信頼を通じて資金が循環すれば、その一部が地域や社会へ還元される。ブロックチェーンは、利益と公益を同時に見える化できる唯一の技術だ。この透明性が、人々の参加意識を高め、善意を経済活動の中に組み込む」と語った。
さらに、デジタル円や円建てステーブルコインの普及が進むことで、小口寄付や地域共助の仕組みも自動化・効率化され、「個人の行動が社会貢献へ直結する金融モデル」が形成されつつあるという。
見崎氏は、「金融は利益を分配するだけでなく、信頼と善意を循環させるべきだ」と強調し、今後は民間企業・自治体・個人が一体となって、テクノロジーを通じて“稼ぐこと”と“助け合うこと”を両立できる社会を目指すべきだと述べた。
リスクと今後の展望
金利変動や発行残高の増減、信用リスクへの対応も課題となる。見崎氏は「ステーブルコインの本質は利回りではなく、信頼コストを最適化する点にある」と述べ、今後は日本銀行のデジタル円(CBDC)との共存や、民間マネーとの相互運用性が焦点になると指摘した。
最後に見崎氏は、「日本のステーブルコインモデルは、金融の再構築だけでなく、信頼を基盤とした新たな価値創造の形だ。金融が社会の善循環を生み出す仕組みとして定着していくことを期待したい」と締めくくった。
责任reporter :news